扶養を外れる前に!
手続きの流れと注意点を分かりやすく解説
パートの仕事時間が増えて収入が多くなったとき・・。
「収入が増えるのに、手取りが減るかも…」
そんな不安を感じた時や、
正社員として就職が決まったときなど、
働き方が変わるタイミングでは夫の扶養から外れる必要があります。
扶養に入る手続きは夫の会社で割と簡単に行えますが,
扶養から外れる場合は、自分自身でも手続きを進める必要があります。
具体的に、扶養を外れるにはどうすればよいのでしょうか?
もし、手続きを忘れてしまったらどうなるのでしょうか?
後で慌てないために、
絶対に知っておきたい大切なポイントを確認していきましょう!
扶養の基本!「税金」と「社会保険」2つの扶養とは?
扶養から外れるタイミングはいつ?
【夫の会社編】妻を扶養から外すときの手続き
健康保険被扶養者(異動)届の提出と保険証の返却
被扶養配偶者非該当届の提出
資格喪失証明書の受け取り
年末調整での申告
【妻自身編】扶養から外れた後の手続き
国民年金の手続き(第1号への変更)
国民健康保険の加入手続き
もし手続きを忘れたら?起こりうる深刻なトラブル
まとめ
参考リンク集
- ページ更新日:9月4日
扶養の基本!
「税金」と「社会保険」2つの扶養とは?
妻が夫の扶養に入る場合、
「税金の扶養」と「社会保険の扶養」という2つの種類を理解しておく必要があります。
・税金の扶養: 年収が103万円以下であること
・社会保険の扶養: 原則、年収130万円未満であること
この2つの扶養を軸に、
働き方を考える上で重要となる、通称「年収の壁」を詳しく見ていきましょう。
扶養の条件となる「5つの年収の壁」
・約100万円の壁(住民税)
これを超えると妻自身に住民税支払い義務が発生します。
(※非課税限度額は市区町村によって多少異なります)
・103万円の壁(所得税)
「103万円の壁」という言葉をよく耳にしますよね!
これを超えると妻自身に所得税の支払い義務が発生し、夫は「配偶者控除」を受けられなくなります。
・106万円の壁(社会保険・短時間労働者)
パート先が以下の条件に当てはまる場合、年収130万円未満でも勤務先の社会保険への加入が義務付けられます。
特に2024年10月から対象企業が拡大されたので注意が必要です。
(週20時間以上・月収8.8万円以上・雇用期間2ヶ月超の見込み・学生でない・勤務先の従業員数が51人以上)
・130万円の壁(社会保険・一般)
上記の「106万円の壁」の条件に当てはまらない場合でも、年収が130万円以上になると夫の社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険などに加入する必要があります。
・150万円の壁(配偶者特別控除)
妻の年収が103万円を超えても、150万円以下であれば、夫は「配偶者特別控除」を満額(38万円)受けることができます。
(この手続きは、夫などが勤務先で行う年末調整の際に申告します)
一般的に、
収入が高くなるにつれて「税金の扶養」→「社会保険の扶養」の順番で外れていきます。
扶養から外れるタイミングはいつ?
扶養の状況は、
会社に提出する「扶養控除等(異動)申告書」という書類で申告します。
この書類には、家族の1年間の収入がどれくらいになりそうか、その「見込み額」を記入する欄があります。
税金の扶養:年末調整で申告
税金の扶養については、
その年の1月1日から12月31日までの1年間の合計収入で判断されます。
そのため、年の途中で収入が103万円を超えても、すぐに手続きをする必要はありません。
「今年は103万円を超えそうだな」と分かったら、その年の最後に行われる年末調整の時に、扶養から外れる申告をすればOKです。
社会保険の扶養:超えると分かった時点ですぐに申告
社会保険の扶養はルールが違います。
こちらは1年間の合計ではなく、
「このままのペースで働くと、年収が130万円を超えそうだ」という将来の見込みで判断されます。
そのため、月収が約10.8万円を超え、年収130万円以上になるのが確実になった時点で、
すぐに扶養から外れる手続きをしなければなりません!
【夫の会社編】
妻を扶養から外すときの手続き

扶養を外れる手続きは、
黙っていても誰も手続きをしてくれません。
自分から申し出ないと、
いつまでも変更されないので注意が必要です!
妻が夫の扶養から外れる際には、
まず夫が自身の会社で行動する必要があります。
健康保険被扶養者(異動)届の提出と保険証の返却
まず、会社の総務や人事など、
社会保険を担当している部署に「妻を扶養から外したい」と伝えます。
担当部署から「健康保険被扶養者(異動)届」を渡されますので、
必要事項を記入して提出しましょう。
このとき書類と一緒に、
妻の分の健康保険証を忘れずに返却する必要があります。
もし担当者が不在だったり、
どこに聞けばよいか分からなかったりした場合は、
会社が加入している健康保険組合に直接問い合わせてみましょう。
被扶養配偶者非該当届の提出
妻が、勤務先の社会保険ではなく市区町村の、
「国民年金」「国民健康保険」に加入する場合には、
「被扶養配偶者非該当届」の提出も必要です。
この届出は、「私はもう第3号の資格がなくなりました」と申告するための大切な書類なのです。
「年金のお知らせ」などで、
扶養に入っている妻が「第3号」と書かれているのを見たことはありませんか?
「第3号被保険者」とは、会社員の夫(第2号被保険者)に扶養されている配偶者のことです。
この届出をしないと、
年金の切り替えがスムーズに行われず、
後から追加で請求されるなど、思わぬトラブルに発展する可能性があります!
資格喪失証明書の受け取り
夫の会社で妻が社会保険の扶養を外れる手続き完了後に、
「資格喪失証明書」を発行してもらいます。
この書類は、
この後の妻自身が「国民年金・国民健康保険」の加入時に必要な重要書類となるので、
必ず受け取りましょう!
もし会社から交付されない場合は、
夫が加入している社会保険の組合などに問い合わせが必要です。
年末調整での申告
サラリーマンの場合、
年末になると会社から年末調整の書類が配られます。
妻を扶養から外した年は、記載内容に注意が必要です。
【「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」】
妻の年収が103万円を超える場合、
配偶者控除の対象外となるため、この申告書に妻の名前は記載せずに提出します。
【「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」】
妻の年収が103万円を超えても、
201.6万円未満であれば「配偶者特別控除」を受けられる可能性があります。
特に妻の年収が、
150万円以下であれば、控除額は満額となります。
対象となる場合は、忘れずに記入して提出しましょう。
【妻自身編】
扶養から外れた後の手続き
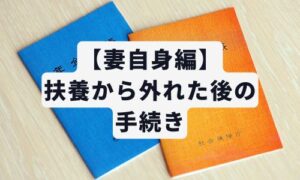
妻が扶養から外れた後、
新しい勤務先で社会保険や厚生年金に加入する場合は、
基本的に会社がすべての手続きを行ってくれます。
年金手帳などを準備しておきましょう。
ただし、個人事業主になる場合や、
新しい勤務先で社会保険の加入条件を満さない場合は、
自分で「国民健康保険・国民年金」への加入手続きをする必要があります。
この切り替え手続きは、
法律で「扶養を外れてから14日以内に行うこと」と定められていますので、
絶対に忘れないようにしましょう!
国民年金の手続き(第1号への変更)
お住まいの市区役所・町村役場の年金窓口へ行き、
「第3号被保険者」から「第1号被保険者」へ種別を変更する手続きを行います。
このとき、
夫の会社で受け取った「資格喪失証明書」や年金手帳、
本人確認書類などが必要になりますので、事前に持ち物を確認しておくと安心です。
国民健康保険の加入手続き
国民年金の手続きと同じく、
市区役所・町村役場の健康保険窓口で加入手続きを行います。
多くの場合、年金の窓口と隣接しているため、一度に手続きを済ませることができます。
必要書類が揃っていれば、
その日のうちに保険証を発行してもらえることもあります。
事前に役所のウェブサイトなどで必要書類を確認してから向かいましょう。
もし手続きを忘れたら?
起こりうる深刻なトラブル
「国民健康保険」や「国民年金」への加入は、
扶養から外れた日から発生する義務です。
もし手続きを忘れて、
扶養に入ったままの状態でいると、どうなるのでしょうか?
不正が発覚した時点にさかのぼって、本来支払うべきだった保険料が一括で請求されてしまいます!
例えば、夫の扶養(第3号被保険者)のままでいると、
本来自分で支払うべき国民年金保険料や国民健康保険料を納めていない状態になります。
これが後から一度に請求されると、家計に大きな打撃を与えることになりかねません。
また、社会保険の扶養から外れたものの、
国民健康保険への切り替えを忘れてしまった場合、
手元に有効な健康保険証がない「無保険」の状態になってしまいます。
この状態で病院にかかりますと、
医療費は3割負担ではなく、全額自己負担(10割)となります。
普段3,000円の診察代なら、10,000円を支払うことになるのです。
入院や手術となれば、その金額はさらに高額になります。
手続きを忘れたままでは、
金銭的にも精神的にも大きな負担を強いられることになってしまいます。
まとめ
扶養に入っている家族は、
税金や社会保険料の面で優遇されています。
しかし、その状況は働き方や収入によって変化します。
妻の収入が増えた場合には、
夫婦で協力し、速やかに扶養から外れる手続きを進めることが大切です。
夫の会社で行う手続きと、
妻自身がお住まいの役所で行う手続きの2段階があります。
必要な書類や期限を確認し、漏れなく対応しましょう。
もし手続きを忘れてしまうと、
後から高額な請求が来たり、
医療費が全額自己負担になったりと、深刻な事態につながる恐れがあります。
そうならないためにも、この記事を参考に、正しい知識を持って行動してくださいね!
参考リンク集
| 公式サイト・サービス | 詳細 |
|---|---|
| 国税庁 公式サイト | 所得税、配偶者控除などの税金に関する公式情報が確認できます。 |
| 日本年金機構 | 年金の被保険者種別や、扶養に関する手続きの公式情報が掲載されています。 |
| 国民健康保険制度について(厚生労働省) | 国民健康保険制度の概要について、国の公式情報が確認できます。 |