出産手当金と扶養制度の完全ガイド!
申請前に知っておきたいお金の話
妊娠・出産は、
女性のライフプランにおける大きなイベントですよね。
新しい家族を迎える喜びと同時に、
お仕事やお金のことで悩む方も多いのではないでしょうか?
特に、産休中の収入が減ってしまうのは大きな不安の一つ。
そんな時に働く女性を支えてくれるのが「出産手当金」という制度です。
でも、この出産手当金を受け取ることで、
夫の「扶養」に入れなくなるケースがあることをご存知でしたか?
出産手当金の基本から、
扶養制度との関係、そして損をしないためのベストな選択まで、
しっかりチェックしていきましょう!
「出産手当金」とは?産休中の生活を支える大切な制度
出産手当金の申請方法|いつ・どこで・どうやって手続きする?
申請から受け取りまでの流れ
出産を機に退職…それでも手当金はもらえる?
要注意!出産手当金と「扶養の壁」の落とし穴
なぜ手当金をもらうと扶養に入れないことがあるの?
損しない選択は?扶養に入るベストタイミングを考えよう
まとめ
- ページ更新日:9月16日
「出産手当金」とは?
産休中の生活を支える大切な制度
産休を取得するのは働く女性の当然の権利ですが、
その間はお給料が支払われないことがほとんどです。
その間の生活費をサポートしてくれるのが、
勤務先の健康保険から支給される「出産手当金」です。
これは、会社の福利厚生ではなく、
健康保険に加入している労働者の正当な権利なので、
条件を満たしていれば誰でも申請できます。
支給される期間
出産手当金は、出産日以前の42日間と、
出産翌日から56日間の合計98日間を対象に、
会社を休んでお給料が支払われなかった日数分支給されます。
(双子以上の場合は、出産日以前が98日間になります)
もらえる金額の目安は?
1日あたりの支給額は、
過去1年間の給与(標準報酬月額)の平均 ÷ 30日 × 3分の2
で計算されます。
例えば、残業代などを含めた年収が350万円だった場合、
1日あたりの支給額の目安は約6,480円。
98日間、満額受け取ると約63万円にもなります!
これは、自分から申請しないと受け取れないお金です。
制度をしっかり理解して、忘れずに手続きすることが大切ですね。
出産手当金の申請方法
いつ・どこで・どうやって手続きする?
出産手当金は、正社員だけでなく、
契約社員やパート・アルバイトの方も、
勤務先の健康保険に加入していれば対象になります。
(産休中も会社から給料が支払われている場合は対象外です)
手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、
流れさえ分かれば大丈夫ですよ!
申請から受け取りまでの流れ
まず、出産予定日がわかったら、
勤務先の担当部署(人事や総務など)に連絡しましょう。
そこで出産手当金を受け取る資格があるかを確認し、
「健康保険出産手当金支給申請書」をもらいます。
この申請書には、自分で記入する部分と、
出産した病院の医師や助産師に記入してもらう部分があります。
医師に記入してもらった申請書を、
産休が終わった後などに勤務先へ提出します。
すると、勤務先が必要事項を記入した上で、
加入している健康保険(全国健康保険協会けんぽ や 健康保険組合)へ提出してくれます。
この流れを経て、
申請から約1~2ヶ月後に指定した口座へ出産手当金が振り込まれます。
支給が決定すると、「支給決定通知書」が自宅に届きますよ!
なお、申請書は勤務先だけでなく、
ご自身が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)や、
各健康保険組合のウェブサイトから、直接ダウンロードすることも可能です。
出産を機に退職…
それでも手当金はもらえる?
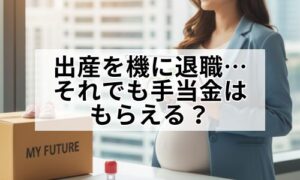
「出産を機に退職するから、自分は対象外かも…」
と思っている方も、あきらめないでください!
実は、出産を機に退職した場合でも、
以下の3つの条件をすべて満たしていれば、
出産手当金を受け取ることができます。
| 退職後に受け取るための3つの条件 |
|---|
| ① 退職日までに健康保険の加入期間が継続して1年以上あること。 |
| ② 出産手当金がもらえる期間内に退職していること。 |
| ③ 退職日に出勤していないこと(有給休暇はOK)。 |
もし申請を忘れていても、
産休開始の翌日から2年以内なら、
さかのぼって申請が可能です!
余談ですが、
もしもお腹の中の赤ちゃんが無事に産まれなかった場合も、
妊娠4ヶ月(85日)以降の出産(死産・流産を含む)の場合は出産手当金の対象となります。
要注意!出産手当金と
「扶養の壁」の落とし穴
出産を機に働き方を変え、
夫など家族の扶養に入ろうと考える方も多いですよね。
しかし、ここが一番の注意点!
出産手当金を受け取ることが、
扶養に入るための障壁になってしまうことがあるんです。
「手当金をもらって、さらに扶養にも入れる」と、
思っていると、後で「しまった!」となる可能性も…。
その理由を詳しく見ていきましょう。
なぜ手当金をもらうと扶養に入れないことがあるの?
家族の扶養に入る(被扶養者になる)と、
自分で国民健康保険料や国民年金保険料を、
支払う必要がなくなるという大きなメリットがあります。
しかし、扶養に入るためには、
「年収が130万円未満である」という条件があります。
いわゆる「130万円の壁」です。
そして、多くの健康保険組合では、
出産手当金をこの「年収」に含めて計算します。
そのため、出産前の給与と出産手当金の合計が、
130万円を超えてしまうと、
その年は扶養に入ることができないのです。
日額3,611円がボーダーライン
扶養の判定では、今後の収入見込み額で判断されるため、出産手当金の日額が重要になります。
具体的には、
日額が約3,611円(130万円÷360日)を超えていると、
「今後1年間の収入が130万円を超える」と判断され、
手当金を受け取っている期間中は扶養に入れない、ということになります。
「出産育児一時金」とは別物です!
ここで一つ注意したいのが、「出産育児一時金」との違いです。
出産育児一時金は、出産にかかる費用を補助するために、子ども一人につき原則50万円が支給される制度です。
(※この金額は2023年4月1日以降の出産に適用されるもので、それ以前は原則42万円でした)
こちらは出産手当金と違い、
扶養を判定する際の年収には含まれませんので、混同しないようにしましょう!
損しない選択は?扶養に入る
ベストタイミングを考えよう
「じゃあ、どうすれば一番損をしないの?」
と思いますよね。選択肢は主に2つあります。
どちらがお得になるかは、ご自身の状況によって変わります。
パターン1:出産手当金を受け取ってから扶養に入る
フルタイムで働いていて、
もらえる出産手当金の額が大きい方におすすめの方法です。
出産手当金を受け取っている期間は、
一時的に国民健康保険と国民年金に自分で加入し、
保険料を支払う必要がありますが、
それを差し引いても、手元に残るお金が多くなるケースがほとんどです。
パターン2:出産手当金は申請せず、すぐに扶養に入る
もらえる手当金の額がそれほど多くない場合におすすめの方法です。
手当金はもらえませんが、
退職後すぐに扶養に入ることで、国民健康保険料などの負担がなくなります。
どちらがお得になるか、
一度、もらえる出産手当金の概算額と、
一時的に支払う社会保険料を計算して比較してみましょう!
まとめ
出産手当金と扶養制度の関係、
少し複雑に感じたかもしれませんが、
ポイントはつかめましたでしょうか?
これまで毎月お給料から支払ってきた健康保険料。
出産手当金は、その保険料を元に、
いざという時に私たちを助けてくれる、とても大切な制度です。
この手の仕組みは、
残念ながら、受給の権利がある人へ親切に教えてくれることはほとんどありません。
まさに「知る人ぞ知る」情報になっているのが現状です。
だからこそ、
知っていて、自分から行動しないと利用できません。
ご自身の状況に合わせて、
出産手当金と扶養に入るタイミングをしっかり計画することで、
お金の不安を少しでも減らすことができます。
正しい知識を身につけて、
安心して新しい家族との生活をスタートさせてくださいね!
参考リンク集
| 公式サイト・サービス | 詳細 |
|---|---|
| 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 出産手当金についての公式な説明や申請書がダウンロードできます。 |
| 厚生労働省 | 日本の健康保険制度全体の概要を確認できます。 |